(現場でのリアルな失敗と学びを伝える記事)
発達障害のある子どもたちへの支援は、日々が試行錯誤の連続です。
支援の正解は一つではなく、子ども一人ひとりの個性や特性に合わせた関わり方が求められます。
ですが、時には「この関わりで本当に良かったのか?」「あの対応は間違っていたのでは?」と悩むこともありますよね。
今回は、私が実際に経験した「うまくいかなかった支援」と、そこから得た気づき・改善策についてご紹介します。
集団活動でうまくいかなかった経験
ある日、複数の児童と一緒に新聞紙を使った“ジャンプ遊び”をしていました。
新聞紙で作ったバーを床に置き、「順番に跳び越える」というルールのもと進めていたのですが、ルールの説明が不十分だったことで事故につながってしまったことがありました。
跳ぶ順番をきちんと決めていなかったため、1人の子が跳んだ直後に、別の子がすぐ後ろから飛んできてしまい、着地中だった子の足に接触し、擦り傷を負わせてしまいました。
対応が不十分だった理由
この時の問題点は、以下の通りです。
- 活動前にルールの説明があいまいだったこと
- 「一人ずつ順番に跳ぶ」という安全面の配慮が足りなかったこと
- 複数の支援員がいたが、全員での事前確認や連携が不足していたこと
楽しく盛り上がっていたこともあり、「多少順番が崩れても大丈夫」と思ってしまったのが甘かったと反省しています。
改善策として行ったこと
この出来事をきっかけに、次のような改善を行いました。
- 活動の前には必ず“安全ルール”を明確に伝える
- 1人ずつ行動する遊びでは目印(マーク)を使って待つ場所を明確にする
- 複数支援員で活動を行う場合は、事前に「どこを見るか」役割分担を確認する
また、子どもたちにも「安全に遊ぶためには、順番を守ることが大切なんだよ」と伝える時間を設けました。
ただ楽しませるだけでなく、“学び”や“気づき”を与える機会に変えていくことの大切さも感じました。
同じような失敗を防ぐために
支援の中で失敗はつきものです。
でも、その失敗からどう学び、どう次に生かすかがとても大切だと実感しています。
同じようなケースに出会った際は、
- ルールは“しっかり伝える”
- 支援員間の連携を怠らない
- 子どもたちの安全確保を最優先に考える
この3つを意識して取り組むことをおすすめします。
おわりに
現場では予期せぬことが起こることもあります。
でも、うまくいかなかった経験は、次の支援をより良くするための“宝”にもなります。
完璧じゃなくても大丈夫。
日々の気づきや失敗を、支援の質に変えていくことこそ、支援職としての大切な力だと思っています。
私の経験が、少しでも誰かのヒントになりますように。

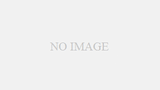
コメント