発達障害のある子どもたちの中には、「こだわり」が強く出ることがあります。
例えば、「毎回同じコップで飲まないと嫌がる」「洋服のタグが気になって着替えを拒否する」など、一見わがままに見える行動も、実は本人にとって“安心できる環境を守るための行動”だったりします。
今回は、実際に支援の現場で出会った“こだわり行動”に対して、どのように関わったかをご紹介します。保護者の方や、支援職を始めたばかりの方の参考になれば嬉しいです。
実際にあった“こだわり”エピソード
ある小学生の男の子は、水を飲むときに「特定の青いコップでしか飲みたくない」という強いこだわりを持っていました。
いつものコップが片付けられていたり、他の子が使っていたりすると、頑として水を飲まず、そのまま不機嫌になって活動にも参加しなくなってしまうことがありました。
当初は「どのコップでも飲めるようになってほしい」という思いから、他のコップを提案してみましたが、拒否されてしまうばかりで、うまくいきませんでした。
私たちが行った対応
まず、「こだわり自体を否定しないこと」を意識しました。
本人にとって、その青いコップは「安心の証」のようなものであり、それを奪われると不安になってしまうのだろうと考えたのです。
そこで、同じ青いコップを数個用意して、「いつものコップがない場合も“似たもので代替できる”経験」を少しずつ増やしていきました。
また、他の子にも「この青いコップは○○くんが安心して使えるように特別なんだよ」と伝え、配慮してもらえるようにお願いしました。
成功した点とうまくいかなかった点
良かった点は、本人の気持ちを尊重しつつ、少しずつ“柔軟さ”を広げていけたことです。青いコップが使えない日も、別のコップで飲めるようになるまでには時間がかかりましたが、子どもの安心感を大切にすることで信頼関係が深まり、徐々に変化が見られました。
反省点としては、最初に無理に別のコップを勧めてしまったことで、強い抵抗を生んでしまったことです。本人の気持ちを置き去りにした対応では、信頼関係を築くどころか遠ざけてしまうことを痛感しました。
他のケースでも応用できる工夫
このようなこだわり行動に対応する際、次のような視点が役に立つと感じています。
- まずは安心できる環境を整えること
- こだわりの背景にある“不安や恐れ”を理解すること
- 「同じではないけど似ているもの」からステップを踏む
- 周囲の大人と協力し、子どもの特性に合った関わりをすること
一人ひとりの子どもに合った方法は違いますが、「否定しない姿勢」と「少しずつ慣らしていく工夫」は共通して大切だと感じています。
おわりに
発達障害のある子どもたちとの関わりには、日々発見と学びがあります。こだわり行動に出会ったとき、「やめさせる」ことに意識を向けすぎず、「どうすれば本人が安心できるか」を一緒に考えていくことで、関係性は大きく変わります。
この記事が、日々支援を頑張っている方や、子育てに悩む保護者の方のヒントになれば嬉しいです。

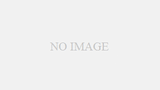
コメント