児童発達支援や放課後等デイサービスの現場では、日常的にさまざまな小さなトラブルが起こります。
子ども同士のけんか、物の取り合い、パニック、ケガ……。
予期せぬ場面に直面したとき、支援者としてどう対応するかはとても大事なポイントです。
今回は、私が実際の現場で意識している「トラブル対応の基本姿勢」と「具体的な対応例」をご紹介します。
トラブルの種類はさまざま
まず、よく現場で起こるトラブル例を挙げてみます。
- おもちゃの取り合いからのケンカ
- 集団活動中の順番をめぐるトラブル
- 環境の変化や刺激で起こるパニック
- 転倒や接触によるケガ
これらは、どれも発達障害の特性や発達段階によるもので、本人がわざと起こしていることではありません。
私が意識している対応の基本
① 安全確保を最優先にする
まずはケガや危険が広がらないよう、物理的な距離をとったり、周囲の子を避難させます。
② 状況を落ち着いて観察する
どの場面から混乱が起きたのか、何がきっかけだったのかを冷静に見ます。
③ 本人の感情を受け止める
例えば「イヤだったんだね」「びっくりしたんだね」と、まず感情を受け止める声かけを心がけます。
④ その場での適切な対応をする
必要なら別室でクールダウンを促したり、落ち着くためのグッズ(ぬいぐるみ・クッションなど)を使うこともあります。
⑤ 後から振り返りを行う
その場を落ち着かせた後で、「何が起きたのか」「次にどうすればいいか」を、本人・他の子・スタッフ間で話し合います。
実際にあった場面と対応例
ある日、2人の子どもがブロック遊び中に「ぼくが先に使ってた!」と取り合いになり、1人が相手を叩いてしまったことがありました。
【対応したこと】
- まずは2人を引き離し、手を出した子の手当てと、叩かれた子の気持ちのフォロー。
- 叩いてしまった子には、「叩いたら痛いよ。でも怒った気持ちはわかるよ」と伝え、代わりの表現(言葉やスタッフを呼ぶこと)を一緒に考えました。
- 保護者には帰りの送迎時に簡単に報告し、必要なら連絡帳で詳細を共有。
こうした対応を積み重ねることで、次第に子ども自身が気持ちを整理する力をつけていけると感じています。
トラブルを「学びの機会」に変える
トラブルはできれば避けたいものですが、完全にゼロにするのは難しいです。
大切なのは、起きたことを責めるのではなく、「次はどうする?」を一緒に考えること。
- 相手の気持ちを知る機会
- 自分の気持ちを伝える練習
- ルールや順番の大切さを理解する時間
こうした「学びのきっかけ」として、支援の中で活かせるよう心がけています。
おわりに
支援現場のトラブル対応は、支援者自身の冷静さと柔軟さが問われる場面です。
完璧な対応は難しいけれど、子どもたちにとって少しでも安心できる場になるよう、これからもチームで試行錯誤を続けていきたいと思っています。
この記事が、支援者や保護者の皆さんのヒントになれば嬉しいです。

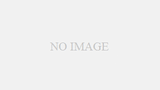
コメント